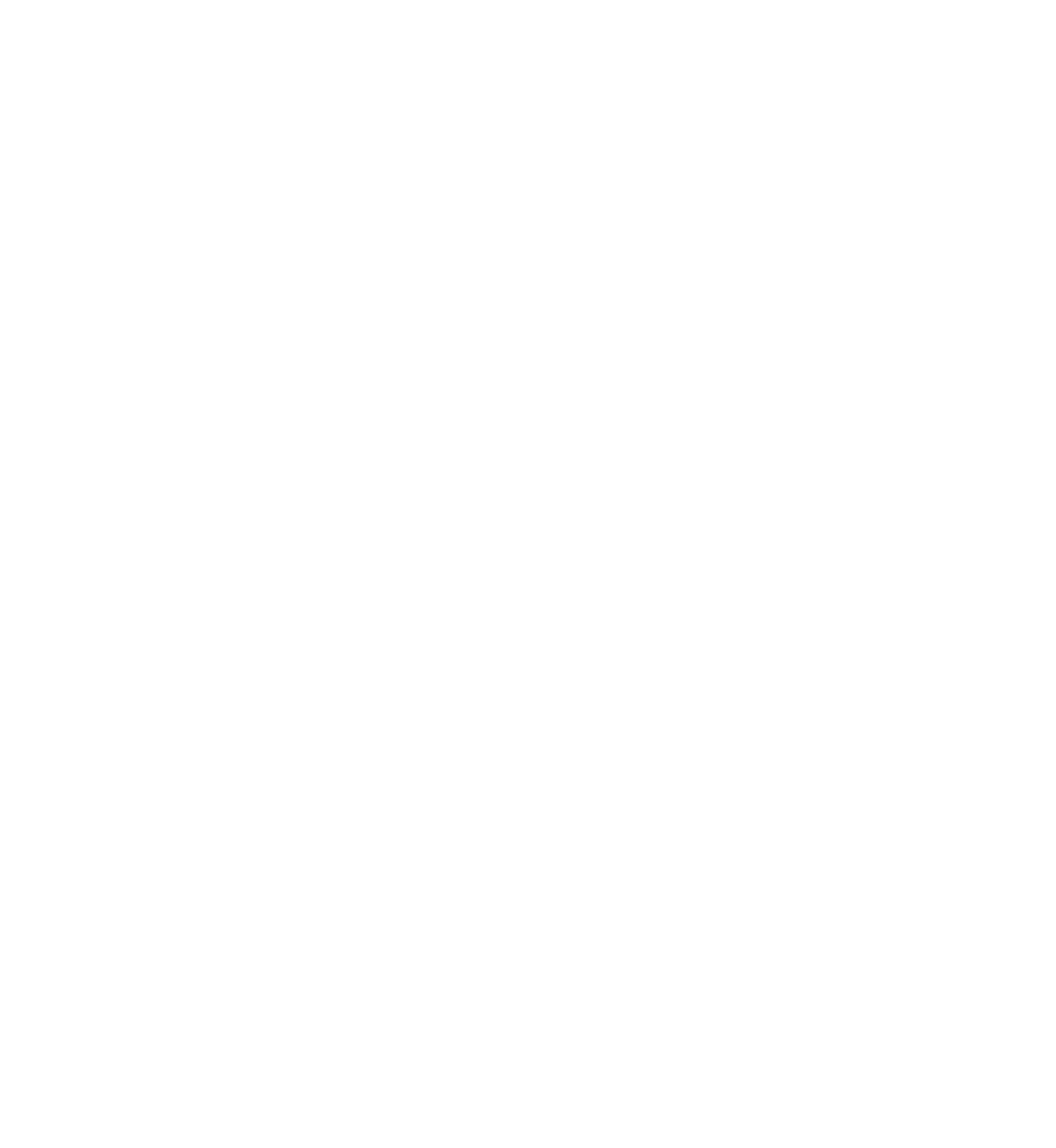
人が真ん中の
醤油をつくりたい。
そんな想いを
ボトルに込めて。
有機大豆仕込みの「白糸の三年醤油」。
そこには、どんな想いが込められているのか。
製造までにどんな苦労があったのか。
小さなボトルの中に込められた、
壮大な物語を紐解いていきます。




不可能と言われた
自然のままの大豆づくり。
「白糸の三年醤油」は、糸島市にある体験型観光農園「白糸の森」を営む前田和子さん、大串幸男さん夫妻が信念を込めてつくった、特別な醤油です。お二人が白糸の森を開業したきっかけは、「農と食を通じて、自然とともに生きることの大切さを多くの人に伝えたい」という想いから。白糸の森の魅力のひとつが、本格手打ちうどんと農場で収穫された新鮮野菜が味わえる「白糸うどん やすじ」です。
お二人は、お客様にうどんを提供する中で、「うどんの味を引き立てる醤油を、白糸の森のコンセプトが反映された独自の醤油にできないか?」と考えるようになりました。そしてついに、農薬や化学肥料に頼らないオリジナルの醤油を、自分たちの手でつくることを決意しました。
そのためには、主となる原料を有機栽培の大豆からつくる必要がありました。しかし、自然の力だけで醤油の原料となる大豆を育てるのは至難の技。「自然のままの大豆をつくることは不可能だ」というのが生産者の常識でした。しかし、「食べることは生きること」が信念のお二人は、「難題であるほどチャレンジする価値がある」ととらえ、大豆づくりの固定観念にとらわれず、大きな挑戦をスタートさせたのです。

収穫できるまでに8年。
大量につくるより質を。
自然栽培の大豆が醤油の原料になるまでには、永い時間が必要でした。「作り始めた当初は、大豆がカメムシにやられてほとんど収穫できませんでした。工夫を重ね、8年以上が経ったいま、ようやく一定量の大豆が収穫できるようになりましたが、まだカメムシの被害はなくなったわけではありません。肥料も一般的なものではなく、自然のものにこだわっていて栄養が限られているため大豆はたくさんできません。ですが、大量につくってそれを売るということよりも、もっと大切なことがあると私は信じています。自然のままでどこまでつくることができるか、こだわりの味をわかってもらえる人にどれだけ届けることができるか。それが私たちの挑戦です」と大串さんは大豆づくりへの想いを語ります。
そしてようやく、8年という気の遠くなるような月日を重ね、醤油の原料となる有機大豆が準備できるようになったのです。

自然栽培にこだわった
実力派の麦を使用。
醤油をつくるうえで大切なのが、醤油の味や香りのもととなる麦。白糸の三年醤油には、自然栽培にこだわっている生産者によって、収穫量より質を大事にしながら生産された麦が使われています。この麦は品評会でベスト3を獲得するほどの実力で、「白糸の三年醤油」の独特の風味に貢献しています。
クリーンな海塩を、
対馬暖流の恵みから。
醤油づくりに欠かせないもうひとつの原材料が塩です。塩味のもととなり、醤油を雑菌から守り、乳酸菌や酵母の働きを促進する塩には、「いちのしお株式会社」のブランド塩を使用しています。いちのしおは、自然豊かな佐賀県加唐島付近を流れる対馬暖流のクリーンで栄養豊かな海水が原料。60℃の低温蒸発でやさしく炊き上げる純国産の自然海塩で、「白糸の三年醤油」の自然な味わいに生かされています。
白糸の森と北伊醤油の
運命的な出会い。
前田さん、大串さんと同じく、「自然のままの伝統的な製法で醤油をつくりたい」と考えていたのが、糸島市で130年近く醤油づくりを続ける北伊醤油の代表を務める山上弘司さんでした。「はじめは、自然栽培で大豆を生産されている農家さんは見つかるだろうと考えていました。しかしそれは甘い考えでした」と開発当初のことを山上さんは振り返ります。自然の力にまかせて大豆をつくることがいかに大変か。「もう無理かもしれない」と山上さんは調べていくうちにその障壁の高さを知ることになります。
2016年、山上さんは、白糸の森を営む前田さん、大串さんご夫妻と運命的な出会いを果たします。「自然を守り未来へ残す。豊かな土を守り育てていく」という理念が生きた、自然そのままの大豆をつくり、その大豆で自然のままの醤油をつくりたい。白糸の森と北伊醤油の想いがそこで共鳴し、製造に向けたチャレンジがはじまりました。そこから長い試行錯誤を経て、多くの失敗と成功を繰り返しながら、ようやく「白糸の三年醤油」が完成したのです。



木桶でなければ
出せない味わいがある。
日本に古くから伝わる伝統的な木桶を使った醤油は、年々減ってきています。タンクを使えば、発酵速度も早いため効率的に多くの醤油を製造することができるからです。現在、流通している醤油の中で、木桶でつくられているものはわずか1%。北伊醤油は、杉が材料の杉桶を用いて、大豆、麦、塩だけを使って天然醸造して醤油をつくっています。杉桶で醸造することで、「蔵付き酵母」が生かされ、その蔵ならではの味わいになっていくのです。
3つの夏を越え、
ゆっくり熟成される。
山上さんは、醤油づくりの繊細な作業についてこう語ります。「杉桶で醤油をつくる場合、自然の酵母で発酵させるために、出来上がりまでに2年半かかります(夏を三回越えることから三夏(みなつ)熟成とも言います)。職人は醤油を見つめ、2年半も醤油に向き合います。酵母や醤油は生きものです。同じように接していても、どれも同じような味わいになるわけではありません。だからひとつひとつの醤油を見て、接し方を変え、独自の味わいをつくりあげていくのです」。
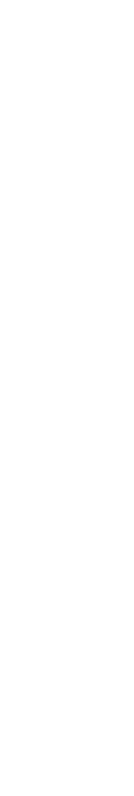
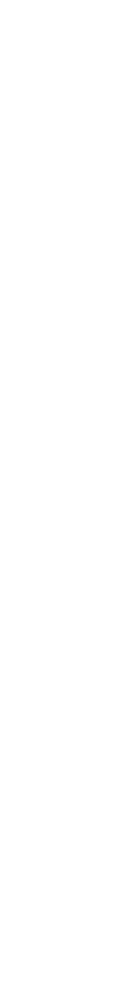
人と自然の営みの大切さを、
日本の未来に残したい。
白糸の森、北伊醤油、いちのしお、麦生産者…。たくさんの人の知恵と自然の恵み、そして時間の力によって「白糸の三年醤油」は誕生しました。前田さんと大串さんは、効率だけを求めていては味の本質を知ることはできないと言います。
「昔はこういう手間暇かかるやり方で土づくりからはじめ、米や野菜、調味料など美味しいものがたくさんつくられていました。私たちは、この醤油を手にした人が豊かな美味しさに触れて、自然の営みや、日本人がずっと昔から大切にしてきたこと、そして自身が生きる意味などを感じ取って欲しいと願っています。そして、その考え方が未来につながっていけばと思います。ものづくりの真ん中にはいつも人がいるんです」。
人が真ん中の醤油「白糸の三年醤油」。それは、醤油瓶に注がれたつくり手の想いが、食卓の真ん中に運ばれ、食べた人に想いが伝播し、その食卓を中心として幸福の輪が社会へ、世界へ広がっていく。そんな醤油なのかもしれません。
テキスト
松田 正志 (文と絵)
商品のご紹介

白糸の三年醤油
出来上がりまでに2年半かかる
(三夏(みなつ)熟成)を行い
キリッとしながらも
最後はふんわりと消えていくような
自然な味わいが特徴です。
原材料: 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国産)
内容量: 200ml








